
この写真は今年の4月、桜が満開の時期に行った時のこと。この哀れな姿の巨大な樹木に驚いて思わずシャッターを切った。たぶん去年の9月の台風にやられたのだろう。まるで血を流しているように見える。
PLANT REVOLUTION (植物革命)
2017年にイタリアで刊行された『植物革命―植物はすでに私達の未来を創っている』は2018年に日本で『植物は未来を知っている』というタイトルで発売になった。
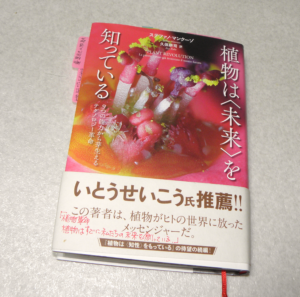
その2年前に発行された『植物は知性をもっている』という本は日本でもベストセラーとなった。こちらの本の方が有名なのだろう。

最初に発売された『植物は知性をもっている』は【序章】のようなものだった。植物学が長い間日陰の道を歩まされてきたせいか、かなり遠慮がちで控えめな感じだった。文章の端々には、現代人の「植物に対する偏見」「見向きもされない学問分野」としての著者の無念さが滲み出ていた。
しかし、続編の『植物は未来を知っている』は、私にとってはとても衝撃的なものになった。
私は定年後のこの2年間、21世紀に突入して以降の情勢に追いつこうと沢山の書物を読み漁ってきた。それらの書物に驚いてばかりの2年間だったが、その中でも最も優れた書物の一冊になった。まだ読んでいない方のために、この書物の内容を紹介していきたいと思う。
『植物は未来を知っている』【目次】
第1章 記憶力 ~脳がなくても記憶できる~ 動物と植物、経験から学ぶのはどちら?/オジギソウの風変わりな実験/オジギソウの記憶力/開花のエピジェネティックな記憶
第2章 繫殖力 ~植物からプラントイドへ~ ダ・ヴィンチとバイオインスピレーション/植物のすごさとは何か?/複数の個体からなる一つの集合体/プラントイドの夢/火星探査へ
第3章 擬態力 ~すばらしい芸術~ モデル、役者、受信者/擬態の女王/植物の視覚/《生ける石》リトープス/植物の資源としての人間/人間と雑草の物語
第4章 運動能力 ~筋肉がなくても動く~ それでも、動く!/植物研究の“革命”/松かさと、カラスムギの芒(のぎ)/オランダフウロと惑星調査/運動モデルのデータを集める
第5章 動物を操る能力 ~トウガラシと植物の奴隷~ ペテンの技術/蜜の密売人/《トウガラシ食らい》との最初の出会い/地球で最も辛いトウガラシを求めて/マゾヒズム、ランナーズハイ、奴隷/化学的な調合
第6章 分散化能力 ~自然界のインターネット~ 植物の体に関するいくつかの予備的考察/問題を解決する植物、問題を避ける動物/根のコロニーと社会性昆虫/古代アテネの民主制/動物たちの民主主義/陪審定理、インターネット、集団的知性/合理的な思考を守る砦/机の上のカオス/インターネット時代の協同組合へ
第7章 美しき構造力 ~建築への応用~ 《葉序タワー》/イギリスの貴族を魅了したオオオニバス/オオオニバスの葉は、初の万国博覧会をどうやって救ったのか?/砂漠を生き抜く植物たち/青銅器時代から未来まで
第8章 環境適応能力 ~宇宙の植物~ 宇宙旅行の道連れ/世紀の放物線飛行実験/天ののけ者
第9章 資源の循環能力 ~海を耕す~ 地球の水のわずか2%/増え続ける食料需要を満たす/海水で生きる/海上に浮かぶ温室で育つレタス/持続可能な未来のために、植物が教えてくれること
以上がこの書物の目次になるが、第1章から5章までは、植物の驚くべき生態を綴っている。前作の『植物の知性』に書かれていることを更に証明していく。ここで、私達は植物に対する価値観、世界観をすっかり変えられてしまうのだ。人間にとって植物は風景の一部に過ぎなかったが、ここで初めて植物が地球の主役に躍り出る。地球上の生命体の99%を占める植物。人間の文明が発達し、人間が地球の主役であるかのように錯覚していた事を思い知らされる。そして、第7章から9章までは植物が持つ「未来の可能性」を語っている。
ところが、この書物はそれだけでは終わらなかった。第6章では書物の中間部にわざとそうしたとしか思えないような展開が拡がる。突然「植物と人間の対比」という論題から、あろうことか、植物学者でありながら政治学者が眉間に皺を寄せるだろう「民主主義」に対する挑戦的な口調が始まるのだ。ここで私の思考は停止してしまい、半年間、第6章について考え込んでしまった。
PARADIGM SHIFT(くつがえる常識)
「パラダイムシフト」という言葉を最近よく耳にするようになった。「革命」とは少し違う。「革命」というと、血生臭く、かつ急激な改革、紛争を連想するが、「パラダイムシフト」はジワジワと進行していく変革、というイメージだ。
これまでの「常識」や「規範」と信じてきたものが、180度違った「常識」や「規範」に置き換えられていく。そんな時代が来ているのだという事を、この書物は教えてくれる。まずは、この書物に書かれている「植物の実態」から入っていこう。そしてこの著者が言わんとする「植物から学ぶ人類の未来のカタチ」について、私なりの理解を書いていきたいと思う。
